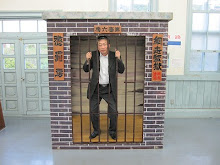朝、富山を発ってお昼ごろ東京に着きました。午後は、アフガニスタンでの医学教育支援のお話をある大学で30人くらいの学生さんにしました。写真はその会場。
実はこの部屋は、教授会にも使われる上等な会議室です。白い巨塔に出てくるのとちょっと似ています。
この部屋には各々にPCが完備されており、自分が話しているときもみなさんはPC画面を見ていらっしゃいます。実はこれが問題で、コミュニケーションには言語的なものと非言語的なものがあり、普通の講演だと表情や身振り手振りといった非言語的な部分でより刺激的に、あるいはわかりやすくお話でき、伝えたいことも伝わり、質問も多いのですが、今回は非言語的コミュニケーションが使えずあまり盛り上がりませんでした。
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーション、どちらが重要でしょうか?両方が乖離した場合を考えればいいのです。深刻な表情の医師に「癌ではありません」と言われた場合、安心できますか? 「あんたなんか嫌い」といいつつしだれかかる女性。非言語的コミュニケーションのほうがはるかに重要と思います。
ところで今述べたような「コミュニケーションには言語的なものと非言語的なものとがある」という言い方、すなわち「2つに分けられる」 という言い方はお話の最初に持ってくると効果的なときがあります。とくに意外性のあるものだと気を引くことができます。
例:人間は相撲取りと相撲取りでない人に分けられます。(意外性)
相撲取りでない人の常識が相撲取りの世界では常識で無いところに今回の問題があります。(ちょっと納得)
「人間は男と女に分けることができます。」 これは意外性が無いのでその後もあまり期待ができないです。
例2:生き物は象と象でないものに分けることができます(意外性)。
この中で象らしく生きられるのは象だけです。そうです、人間らしく生きられるのは人間だけなのです。みなさん、人間らしく生きましょう。象らしくは生きられないのですから・・・
何か面白い対比はあるでしょうか?どこかで使わせていただきますので、あったら教えてください。
蛇足ですが、この手法は、「人間は金持ちと貧乏人に分けられる」というように途中のグレイゾーンを無視して両極端を対比させることによって議論を際立たせているのですね。
だから、「人間は男と、女と、性同一性障害者に分けられる」とすると、どうも議論がまとまらないようです。2つに分けるのがコツです。